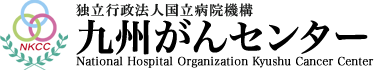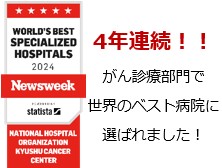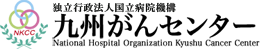診療内容
リンパ管静脈吻合術によるリンパ浮腫治療
形成外科は、組織移植の一手段としてマイクロサージャリーを行っています。これは3mm以下の血管を顕微鏡下で吻合する手技で、皮弁や筋皮弁の移植、指の再接着、移植治療の脈管吻合など多くの手術に使われています。この技術をさらに修練すると0.3mm〜0.5mm のリンパ管の吻合が行えるようになります。この手技により、リンパ浮腫の治療として顕微鏡下のリンパ管静脈吻合という新しい手術が行えるようになりました。乳がんや子宮がん・前立腺がんなどの術後で、リンパ浮腫で悩んでおられた患者さんの新しい治療法として注目されています。侵襲が少ない手術であるにも関わらず効果が期待できる方法で、吻合本数を限れば局所麻酔で行うことも可能です。当院にはリンパ浮腫のテラピスト資格を持つ看護師によるリンパ浮腫ケア外来があり、手術だけでなく術前・術後のドレナージや圧迫などの複合的加療も行える体制を整えています。複合的加療によってある程度浮腫を改善させてから手術の適応を検討することで、手術効果の長期的な維持が期待できます。リンパ浮腫の手術と術前・術後のケアがチームで行える数少ない施設として、リンパ浮腫に悩む患者さんのお役に立ちたいと思っています。
※リンパ浮腫ケア外来は自由診療です。基本的に当院でがん治療をされた方を対象としておりますが、形成外科でのリンパ管静脈吻合を希望される場合は、他院でがん治療をされた患者さんにも対応しております。 →リンパ浮腫ケア外来はこちら
腫瘍切除後の再建
患者さんの病態によっては複数の診療科が協同で手術を行うことがあります。それぞれの科が専門性を生かした手技を担当することで、より高度で安全な手術が行えるようになります。このような協同手術において形成外科は主に組織移植で欠損部を作り治す“再建手術”を担当しており、近年手術件数増加とともに協同で手術を行う診療科も増えています。 がんの手術によって呼吸、食事、会話、整容など日常や社会生活において重要な機能が失われると、その後の生活に大きな支障を来します。当科では組織移植の手法を用いてこれらの障害を最小限に抑えて日常の生活に戻れるお手伝いをするとともに、術後の合併症を減らすことでがん治療を側面から支えています。
乳房再建
2013年より人工乳房による乳房再建が保険診療適用となり、乳がん治療に伴う再建の選択枝が増えました。九州がんセンターは、組織拡張器挿入とインプラント挿入による再建が一次・二次ともに行える認定施設でもあり、乳腺科と形成外科のチーム医療で、切除と再建の両方の適応を十分考慮した高度な治療が可能となっています。また、2020年より遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)に対する予防的乳房切除と再建術が保険診療適用となり、当院でも対応しています。
乳房再建用インプラントに関連してまれに悪性リンパ腫が発生することが近年報告されています。また、放射線治療を行った患者さんでは人工乳房による再建手術の合併症が多くなります。当科ではこれらのことを踏まえ、2021年より背中や下腹部など自分の体の他の部位から組織を移植する自家組織移植による乳房再建術を開始しました。患者さんの状況やご希望を伺い、それぞれに合った手術法を相談していきます。
がんセンターで最終的にインプラントを挿入した患者さんで、1年以上形成外科を受診されていない方は受診予約をされて下さい。乳房再建用インプラントに関連してまれに起こる悪性リンパ腫についての情報をお伝えいたします。過度な心配はいりませんが、定期的な診察が必要です。(別の施設でインプラントを入れられた方は、挿入したインプラントの情報はその施設で記録し、登録・管理してありますので、そちらでお尋ねください。)
診療実績
リンパ管静脈吻合術の件数
| 年 |
件数 |
| 2022年 |
8 件(リンパ浮腫ケア外来受診者数 のべ231人、うち新規受診者数21人) |
| 2023年 |
18 件(リンパ浮腫ケア外来受診者数 のべ261人) |
※ 同一患者さんに複数の吻合を行った場合は1件で集計。
腫瘍切除後の再建件数(乳房以外)
| 年 |
件数 |
| 2022年 |
67 件(空腸移植20件、遊離皮弁18件、有茎皮弁19件、局所皮弁4件、血行再建(血管吻合)5件、神経再建1件)
|
| 2023年 |
61 件(空腸移殖13件、遊離皮弁24件、有茎皮弁19件、局所皮弁7件、血行再建(血管吻合)3件、神経再建1件、皮膚移植6件)
|
※ 同一患者さんに複数の再建を行った場合は個別に集計。
乳がんの再建件数
| 年 |
件数 |
| 2022年 |
28 件(組織拡張器挿入16件、人工乳房9件、自家組織移植3例) |
| 2023年 |
29 件(組織拡張器挿入18件、人工乳房9件、自家組織移植2例) |
※ 同一患者さんに複数の再建を行った場合は個別に集計。
担当医表
| 受付時間 |
9時~11時 |
| 外来診察室 |
形成外科(Jブロック) |
| 初診(初めて)の方 |
代表番号 |
TEL 092-541-3231 |
| 再診(再来)の方 |
予約センター |
TEL 092-541-3262 |
※紹介または受診の場合は、診療内容および予約の確認のため、上記に事前にご連絡ください。
※医師の学会出張や業務の都合による急な休診・代診が発生する場合がございます。
※初診時は絶食不要です。来院後は基本的に水分(水やお茶)のみ摂取可としていますが、食事をとりたい場合には必ずスタッフに確認をお願いいたします。